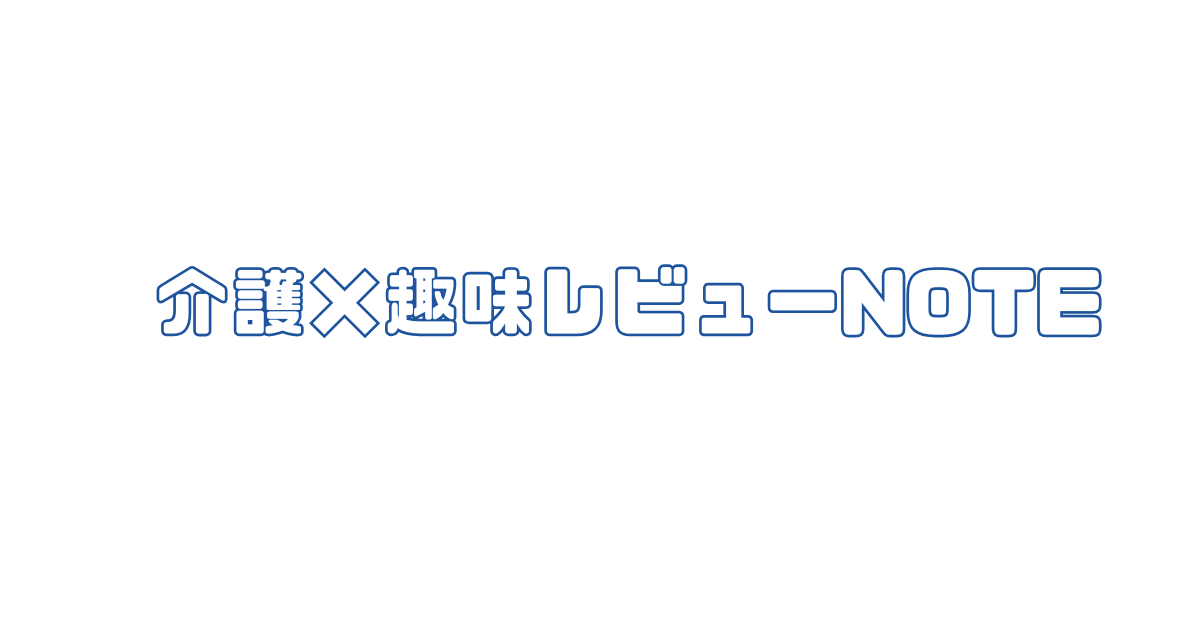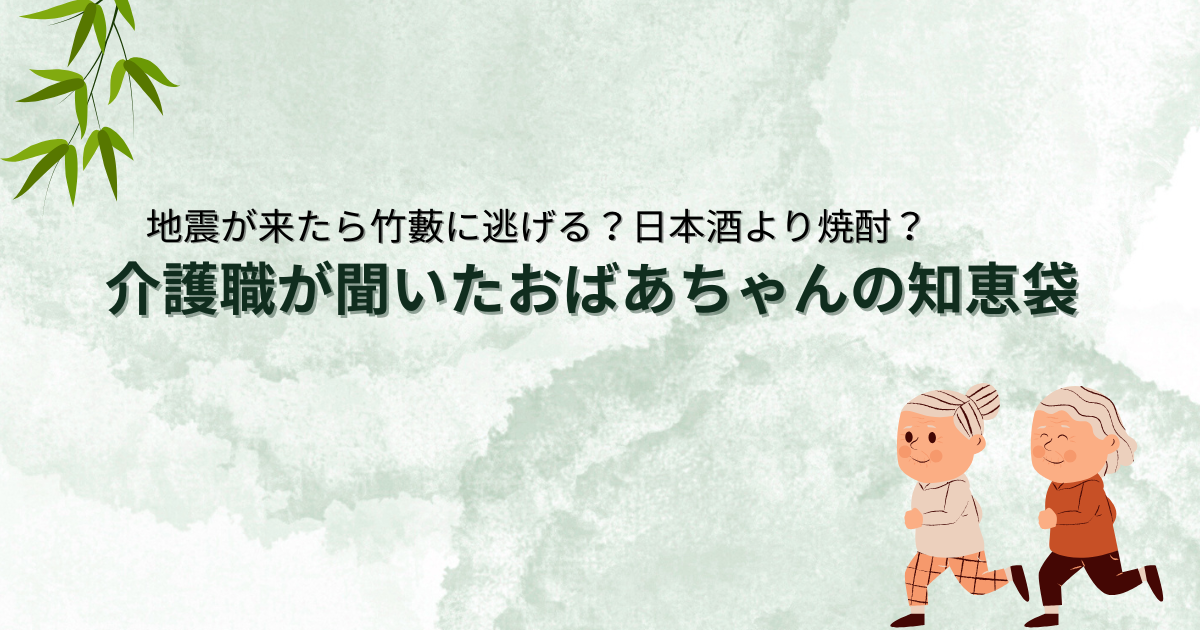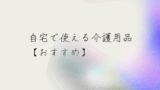私は介護の仕事をしているのですが、日々ご利用者さんと関わる中で「なるほど」と思わされる場面がよくあります。特に印象に残るのは、人生の大先輩であるお婆ちゃんやお爺ちゃんから聞く、昔ながらの知恵袋 です。
例えば、地震のときの避難先の選び方、お酒と健康の関係、そして長生きの秘訣。
どれも一見すると「昔話の一つ」に聞こえるかもしれません。
けれど、現場で耳にしたその言葉をあとから調べてみると、現代の科学や公的な研究と不思議と重なる部分があるのです。
私は介護職として「お年寄りの声には、長年の経験からくる実感がある」と感じています。
お年寄りのことばではないけど、『笑う門には福来る』などのことわざも、ある種【引き寄せの法則】であると思っています。
だからこそ、今日はその知恵袋を取り上げつつ、信頼できるデータと照らし合わせながら「本当に役立つ生活のヒント」としてまとめてみたいと思います。
地震の時は竹林に避難せよ?
お婆ちゃんの知恵
「地震の時は竹のある場所に避難するといい。竹は根が張ってるから安全なんだよ」
これは、施設で暮らすお婆ちゃんから聞いた言葉です。
昔の暮らしでは竹林が身近にあり、安心できる避難先としてイメージされていたのかもしれません。
竹の「根張り」が与える安全感
竹の根は広がって地面をしっかりと固定するように張り巡らされている。
そのため、お婆ちゃんの感覚としては…
地面が崩れにくい 。
大木のように根元から倒れにくい 。
周囲の土をつなぎとめる力がある 。
といった安心感につながっていたと考えられます。おばあちゃんに『なんで?』と聞いたところ、『そう教わったんだよ』と言ってました。
実際の事例と専門家の見解
私なりに調べたところ、ウェザーニュースの記事によると、1947年の昭和東南海地震や2011年の東日本大震災では、竹藪に逃げて助かった人の証言 があるといいます 。
竹はしなやかで倒れにくいため、直感的に「揺れに強い」と感じられるのでしょう。しかし同記事では、農林水産省の調査をもとに、竹の根は浅く横に広がるため、逆に土砂災害を引き起こす危険性がある という指摘も紹介されています。【参考:ウェザーニュース】
つまり「竹林=必ず安全」とは限らないということです。竹藪と竹林の違いもあるようですね。
公的防災指針との比較
消防庁や自治体の防災ガイドでは「揺れが収まったら、広場・公園・避難所へ避難」と明示されています。 竹林を公式の避難場所とするケースはほとんどなく、むしろ「木が少ない広場」が優先されます。 特に谷沿い・斜面沿いの竹林は、逆に土砂災害リスクが高いため注意が必要です。
竹藪に逃げる編まとめ
お婆ちゃんの「竹林避難の知恵」は、
自然に根ざした暮らしから得られた直観 根張りや柔軟性といった、竹の特性への信頼 に基づいていました。
ただし、現代の防災の観点では「竹林=絶対に安全」とは言えません。
最も重要なのは 地域のハザードマップと指定避難所の確認 であり、竹林はあくまで「緊急時に一時的に身を寄せる場所」として考えるのが現実的でしょう。
お酒と長寿:日本酒より焼酎がいいっていう話
お婆ちゃんの知恵
また違うお婆ちゃんがこう言っていました。
「日本酒好きな人は長生きしなかった。焼酎の方がいいよ」
この言葉には、過去の経験則や身近な観察が反映されている可能性があります。
昔は日本酒が主流だった時代に、酒癖や体調の差を各自で感じていたのでしょう。
この知恵をそのまま「真実」とするのではなく、「どこまで根拠があるか」「どういう条件なら成立しうるか」を現代のデータと照らし合わせながら検証してみます。
日本酒と焼酎、それぞれの特性・違い
日本酒は米を発酵させて作る「醸造酒」で、糖質を含みます。一方、焼酎は蒸留によって作られるため糖質がほとんど含まれず、すっきりした味わいです。
この「糖質ゼロ」という特徴が、健康面での優位性として語られることがあります【出典:たのしいお酒.jp】。
科学的な検証
実際の研究を見ると、「どのお酒を飲むか」よりも「どれだけ飲むか」の方が健康リスクに強く影響します。
国立がん研究センターの多目的コホート研究では、1日2合未満の飲酒ではがんのリスクは大きく上がらないものの、2合以上になるとリスクが1.4倍以上になると報告されています【出典:国立がん研究センター】。
一方、蒸留酒(焼酎・ウイスキーなど)をよく飲む人の方が死亡率が高いという報告もあり、必ずしも「焼酎が健康にいい」とは限らないことが分かっています【参考:ダイヤモンド・オンライン】。
焼酎のほうがいい編まとめ
お婆ちゃんの言葉には「糖質の少ない焼酎は体にやさしい」という直感が表れていました。確かに一理ありますが、現代の研究では「酒の種類よりも飲酒量が重要」という結論が出ています。
つまり、焼酎だから長生きできるわけではなく、適量を守ることが大切。この知恵は「飲み方に気をつければ健康を守れる」というメッセージとして受け取るのがよさそうです。

お婆ちゃんも『コップ一杯くらい』って言ってました。
長生きの秘訣は “人と話すこと・働くこと”?
お婆ちゃんの言葉
別のお婆ちゃんはこう言っていました。そう、お婆ちゃんばかりなんです。
施設にはなぜか男性利用者が少ない…
「家に篭ってばかりじゃダメだよ。人と話して仕事をすると長生きする」
この言葉には、「身体を動かす」「社会との接点を持つ」「役割を持つ」といった要素が暗に含まれているように思います。
現代の研究から、この知恵がどれくらい裏付けられているのかを調べてみました。
社会参加・人との交流は健康にどう効くか?
「社会参加」と「健康・長寿」の関連
まず、日本国内でも「高齢者の社会参加・社会関係と健康・介護予防」についての研究が多くあります。
「高齢者の社会参加は主観的・客観的健康度の向上につながる」ことが報告されています。 【出典:健康長寿ネット】
社会参加(就労、ボランティア、地域活動など)と生活機能維持・要介護化予防との関連を縦断データで調べた研究もあります。
特に “月に1回以上社会参加している高齢者” は、社会参加していない高齢者に比べて「人生最後まで自立を維持するパターン」をたどりやすいという研究成果もあります。 【参考:京都大学 社会疫学分野】
また、厚生労働省の「健康長寿ネット」などでは、社会参加を通じて「孤立を防ぐ」「精神的な活力を保つ」ことができる、という見解が紹介されています。 【出典:健康長寿ネット】
これらのことは、「話す・働くなど人と関わること」が単なる気休めではなく、実際に身体機能・認知機能・心理的な健康を支える要素になりうるという裏付けになります。
「社会参加の種類」「開始時期・頻度」の影響
ただし、すべての社会参加が同じ効果を持つわけではありません。条件や形態によって効果が異なるという研究もあります。
複数の活動に参加するほうが、健康効果が高いという報告があります。【出典:健康長寿ネット】
強制的・ノルマ的な活動、過度に負荷の高い活動はストレスになりうる、という注意も示されています。
また、年齢・性別・健康状態によって、社会参加が効果を発揮しやすいパターンと、逆に負荷になる可能性もあるという報告があります。
つまり、「無理のない範囲で、自分に合った関わり方を続けること」が鍵と言えそうです。
人と話して、仕事をすると長生きする編
お婆ちゃんの知恵「人と話して仕事をすると長生きする」は・・・・
- 孤立防止
- 役割意識の保持
- 身体活動や外出の増加
- 精神的な活力維持
といった面で科学的にも裏付けがあると言えます。
ただし「無理のない範囲で」「自分に合った方法で」関わることが重要です。
この知恵は、現代の研究に照らしても 十分に実践価値がある長寿の秘訣 として活かせるでしょう。
まとめ:お婆ちゃんの知恵袋に学ぶ、現代でも役立つヒント
- 地震のときは竹林に避難する
- 日本酒より焼酎のほうが長生きにいい
- 家に篭らず、人と話して仕事をするのが長寿の秘訣
一見すると「昔の人の言い伝え」ですが、調べてみると現代の防災科学や医学研究と意外と重なる部分があることが分かりました。
- 竹林は柔軟で倒れにくい一方、土砂災害の危険もあるため「必ず安全」とは限らない。
- 焼酎は糖質が少ない分メリットはあるが、飲み過ぎれば健康リスクはどのお酒でも変わらない。
- 人と話し、社会参加することは、孤立防止や心身の健康維持に役立つことが多くの研究で確認されている。
つまり、お婆ちゃんの知恵袋は 経験から生まれた“実感のある言葉” であり、それを科学や公的データで検証すると「今でも役立つ暮らしのヒント」として活かせることがわかります。
これからの時代、私たちが健康に、そして安心して暮らしていくためには、
昔の知恵を大切にしつつ 科学的な根拠を踏まえて取り入れる。そんなバランス感覚が必要だと感じます。

もっと色んなこと教えてもらお!