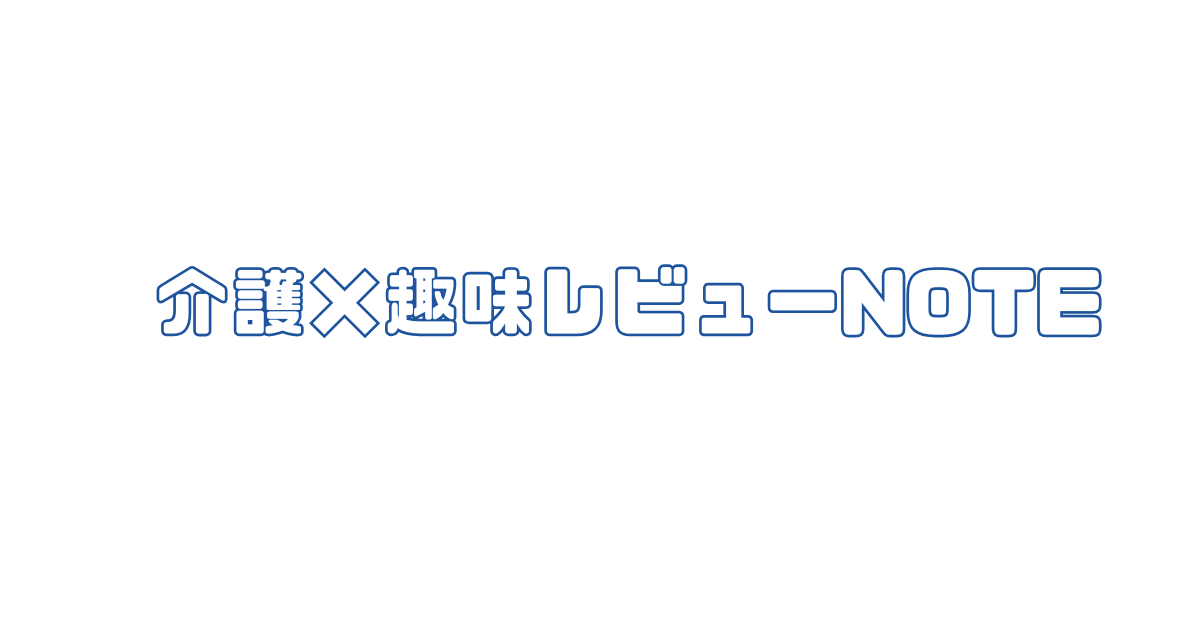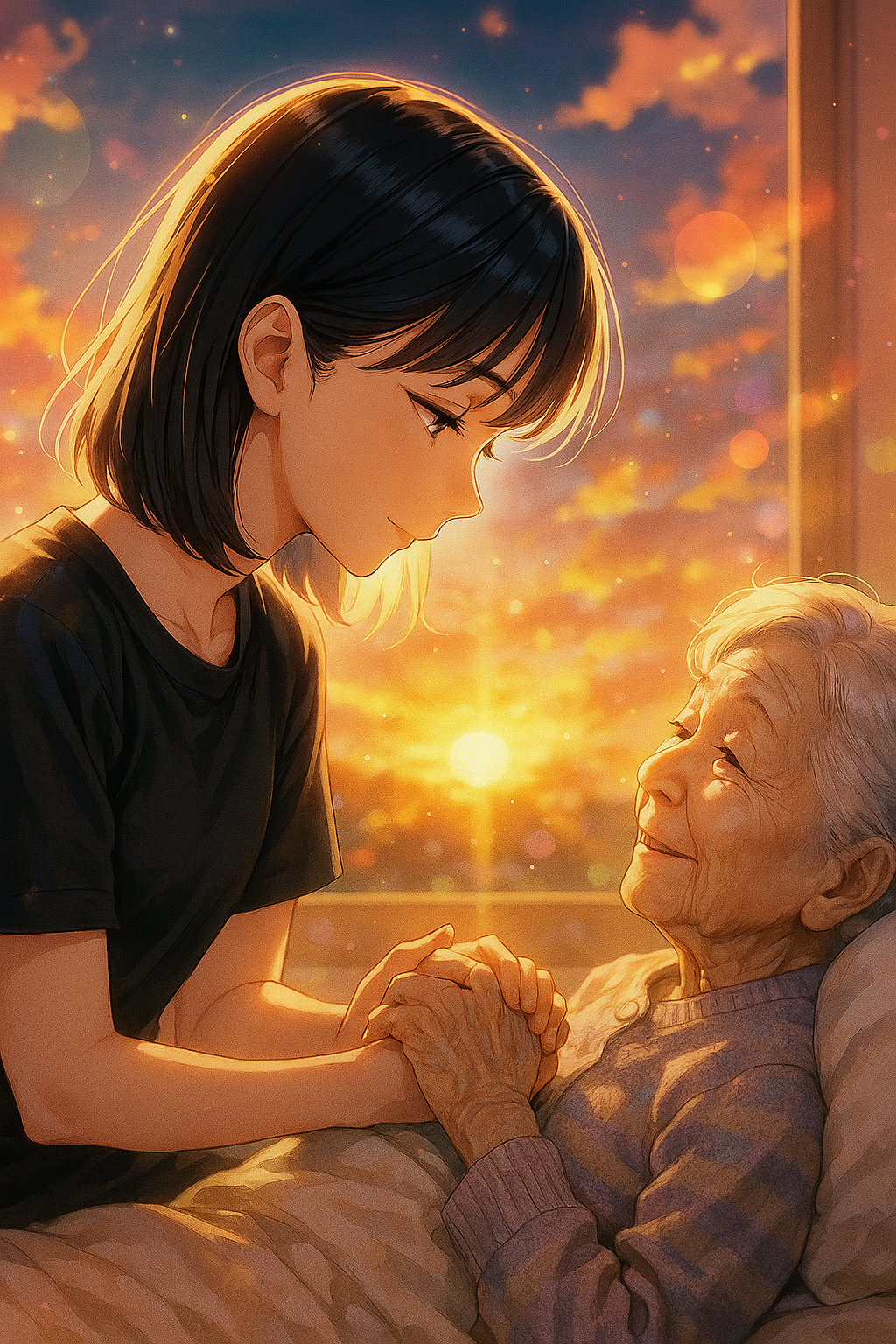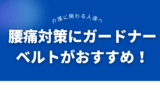ユニット型特養(ユニットケア)とは?その魅力を徹底解説
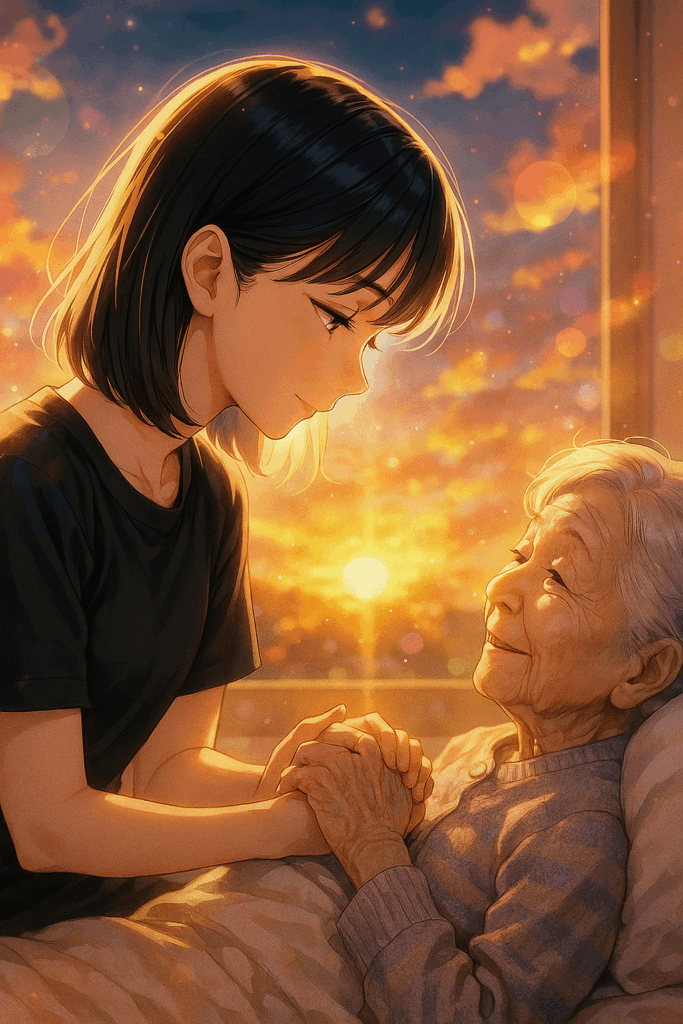
「ユニット型特養(特別養護老人ホーム)」とは、10人前後の少人数グループごとに生活空間を分け、家庭的な環境を再現した新しい介護施設の形です。最大の特徴は「全室個室」と「共有リビング・キッチン」の組み合わせ。
利用者は自分のプライバシーを守りながら、リビングでは他の入居者や職員とゆるやかに交流できる。
そんな“暮らしに近い”空間が用意されています。施設によるかもしれませんが、個室に自宅で使っていたテレビやタンスも持ち込めます。愛着のある物が身辺にあると落ち着きますからね。
このスタイルには、利用者にとっての大きなメリットがあります。生活リズムを自分で選びやすく、ストレスの少ない環境で安心して過ごせる点が好評です。
一方、介護職員にとっても、少人数ケアだからこそ利用者との信頼関係が築きやすく、個別ケアの質を高めやすいという魅力があります。
「ただの作業じゃない、本当のケアができる」
と感じられる現場なんです。
しかし、この理想的な環境を支えるには、それなりの人手と体制が必要。
このユニット型の裏にある「人手不足の現実」が問題なんです。
ユニットケアのデメリット|人手不足と崩壊の現実
理想のケアができるはずのユニット型特養。でも、現場では深刻な「人手不足」が続いてるのが現実です。
赤字にならず、人員が潤っているホワイト施設はあるのでしょうか?
ユニット型は少人数ケアだから、どうしても「手厚い人員配置」が求められます。1ユニットに対して常に職員が1人は必要で、夜間や休憩中もカバーしなきゃいけない。
つまり、通常の施設以上に人が必要です。
でも実際には、職員の確保がかなり厳しい。
理由はいろいろあるけど、まず大きいのが「賃金の低さ」と「業務の過重さ」。
他業種と比べて給料が少ないのに、身体的・精神的負担はめっちゃ大きい。
そりゃ、長く続けにくいのも無理ない。
誤薬、見守り不足による転倒、誤嚥、どれもちょっとした油断から起きてしまいます。
さらに、若手が育ちにくい環境や、管理者の負担の大きさも離職の原因。
人が減れば、残った人の負担がもっと増えて…っていう悪循環が起きてるのが実態。
(コロナの時は大変でした汗)
離職理由の多くは人間関係|ユニットケア現場で起きる問題
私は辞めたいとは思いませんでしたが、人間関係を良好にしたかったので色んな本を読んで勉強しました。考え方ですよね。
相手の人も自分と同じで、1日を送っている。色んなことが起きてる。
だからイライラする日もあるし人に当たりたくなる日もある。
毎日同じ人だけど、中身は昨日と少し違う人。
苦手だなっていう思い込みを捨てる。
間違った解釈だったら申し訳ないですが、これがすごく自分のためになりました。
自分を変えたい、人間関係に悩んでるって人いたら読んでみてください。
地域差や施設の規模によっても状況は違うけど、共通して言えるのは「理想に見合うだけの人材が確保できていない」ってこと。
理想、法人理念に沿った介護をするには人が足りないんです。
これが次のシフト問題にもつながっていきます。
シフトが組めない問題|人手不足で回らないユニットケアの現状
ユニット型特養で深刻な問題の一つが、「シフトが回らない」ってこと。これは人手不足とも強く関係してるけど、ユニットケア特有の構造も影響してるんだよ。
まず、ユニット型では1ユニットごとに専属のスタッフが必要。Aユニットの職員が急に休んでも、Bユニットの職員が簡単にカバーできない。つまり、代わりが効きにくい仕組みなの。
さらに、日勤・早番・遅番・夜勤といった複雑なシフトを、限られた人員で回すのは至難の業。月末になると「もう誰もいない…」って上司が頭抱えてることも少なくないんだよね。
残業でこなすか、休日出勤するか、結局そうなります。
職員一人ひとりの希望休や体調にも配慮が必要だし、現場が疲弊していくのは当たり前。でも放っておくと、さらに離職者が増えて、シフトはもっと厳しくなる。
このループなんです。
潤う→辞める→残った人疲れる→異動して補充→潤う→残った人が安心して辞める→辞める
- 辞める対象が変わるだけなんです。
- 根本を解決しないとダメなんです。
- この悪循環をどう断ち切るかがカギ。
業務的な問題では、最近では、ICTやAIを活用してシフト作成や業務の見える化を進めている施設もあります。ちょっとした仕組みで現場の負担を大きく減らせる可能性がある。
けど問題が人間関係かもしれない。リーダーが動いて早めに手を打ちましょう。
そうしないと、やがて施設全体の問題になります。
そのユニットで誰かが辞めたら、誰かが異動しなければならないですから。
人手不足のユニットは、根本の原因を見つけよう。
ユニットケアで虐待問題が起きる背景|人手不足とストレス構造
介護現場における「虐待」。ニュースで取り上げられるたびに大きな衝撃がありますが、その背景には単なる個人の問題を超えた“構造的課題”が存在しています。
まず根本にあるのは、慢性的な人手不足です。職員が常にギリギリの人数で勤務している状況では、休憩も取れず、心身ともに余裕を失っていきます。
その結果、小さなストレスが積み重なり、感情的な対応や過剰な言動へとつながってしまうのです。
また、ユニット型特養は少人数制であるため、毎日同じ利用者と深く関わることになります。本来は信頼関係を築きやすい環境のはずが、逆に関係性が悪化した場合には逃げ場がなく、職員が精神的に追い詰められるケースもあります。
加えて、ケア方針に対する意見のズレや、十分なサポートを受けられない管理体制など、組織全体の問題が虐待の芽を見逃す要因にもなっています。
個室だから何が起きてるか分かりませんからね。
虐待を未然に防ぐには、以下のような仕組みが重要です。
- • 職員のストレスを軽減する仕組み
- • 心理的安全性のある相談環境
- • 管理職やリーダーの支援体制の強化
職員が安心して働ける職場こそが、利用者にとっても安全な環境になります。
つまり、虐待対策は「人」ではなく「環境」を見直すことから始まるのです。
ユニットリーダーは職員の様子にも注視しましょう。
職員の負担を軽減できる部分はレクレーション
介護現場では、日々の業務が忙しく、利用者さんのためのレクリエーション活動を企画する時間が限られていますよね。
現場で働いているから分かりますが、排泄や入浴介助、認知症対応はいつもいる職員がやるからこそ意味があると思っています。利用者さんをよく理解している現場の介護職がやった方がいいでしょう。
けれどレクレーションの時間帯なら、職員の負担を軽減できると思います。
より質の高いレクリエーションを利用者さんに提供するのも素晴らしいと思います。
何より職員にとっても、勉強になることでしょう。
エブリ・プラスは、介護施設やデイサービス向けに、レクリエーション活動を簡単にマッチングできるサービスです。利用者さん一人一人の状態に合わせたアクティビティを提案し、職員が手間なく楽しく提供できるようサポートします。
ただのレクリエーションにとどまらず、多彩な講師が揃い、さまざまなジャンルのアクティビティを提供しています。
たとえば、マジックで利用者さんを笑顔にしたり、体操で健康促進を図ったり、昭和歌謡で懐かしの歌を楽しんだり。
さらに、寿司職人による実演や、ドッグセラピーで癒しのひとときを提供することも可能です!
これだけのジャンルが揃っていれば、利用者さん一人一人に合わせた、飽きのこないレクリエーションが提供でき、施設の魅力アップにも繋がります!

未来のユニット型特養に必要な人材育成と待遇改善
ユニット型特養が本来持つ「家庭的で個別性の高いケア」を実現するには、今のままでは限界があります。これからの時代に求められるのは、『人が育ち、長く働ける環境づくり』です。
まず最優先すべきは人材の定着。そのためには給与水準の見直しだけでなく、研修制度やキャリアパスの明確化が不可欠です。
介護職が“専門職”として誇りを持ち、やりがいを感じられる仕組みが必要です。
ですが、今の若い方たちは出世欲ないと聞きますからそこは聞いたほうがいいかも。
あるいはどんな風に後輩のモチベーションをあげてあげるかを考える!
仕事なのか、お金なのか、家族なのか、
恋人なのか、自分のためか、あるいは理想の介護をしたい、かもしれない。
人によって仕事をする理由は違いますから。
次に、ICTやテクノロジーの積極活用もポイント。記録業務やシフト作成、見守り支援などをデジタル化することで、業務の効率化と職員の負担軽減が可能になります。
その分、利用者との関わりに時間を使えるようになります。
さらに、多職種連携や地域とのつながりも重要です。ユニット型は閉鎖的になりやすい分、外部との連携が欠かせません。看護師、機能訓練指導員、栄養士、家族、地域住民など、関係者との情報共有や支援体制が施設の質を左右します。
未来のユニット型特養は、「誰もが安心して暮らし、働ける場所」へと進化するべきです。そのためには、現場からの地道な改革と、仕組み全体を見直す視点が求められています。
ユニットケアが崩壊しないために|これからの課題と解決策
ユニット型特養は、「個別ケアの充実」と「家庭的な生活環境」を両立させる、今注目の介護施設です。
全室個室・少人数ユニットという仕組みは、利用者のQOL(生活の質)を高め、職員にも“やりがい”をもたらす環境として期待されています。
しかし現実は、人手不足・シフト調整の困難さ・職員のストレス・そして虐待リスクといった深刻な課題に直面しています。理想を実現するには、現場にのしかかる構造的な負担を軽減する仕組みが不可欠です。
そのために必要なのは以下の3つの視点です:
- ICT・テクノロジーの活用による業務効率化と負担軽減
- 職員の定着と育成を支える制度・キャリアパスの整備
- 多職種連携と地域との協働によるチームケアの実現
ユニット型特養は、“人を支える場所”であると同時に、“人が育つ場所”でもあるべきです。
制度やテクノロジーだけでなく、「職員一人ひとりが安心して働ける環境づくり」こそが、虐待や離職のない未来への鍵を握っています。
シンプルに働きやすい職場づくりってことなんですよね。
色々不安なこと書きましたが、私は特養が好きですよ。
主役は私じゃないですが、誰かの人生の脇役になれるならそれでいいかなと思います。