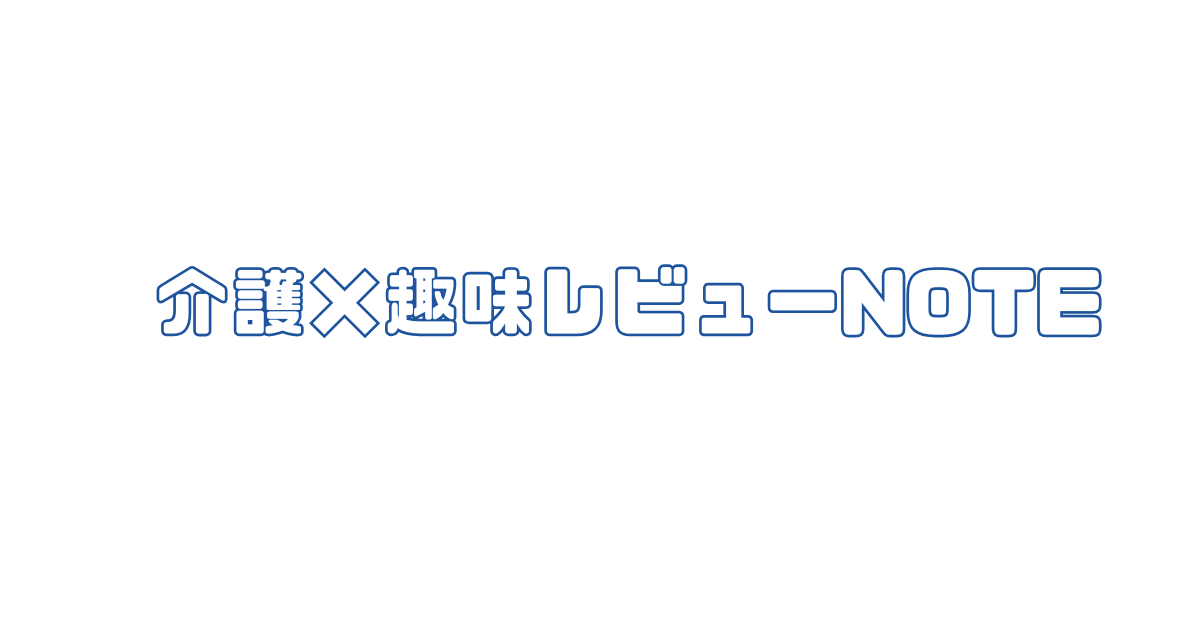何が“決まりそう”なの?現場に関係ある?
ケアマネ試験を受けたので、先日このニュースを見て「やっぱり」と思いました。
やっぱり、というのは色々な方のYOUTUBEを見て「変わる」と予想している方が多かったからです。

更新費用、特に変えてほしいです。
- 厚労省は2025年10月27日の社会保障審議会 介護保険部会に、ケアマネ受験資格の実務経験「5年→3年」への短縮案と、対象資格の見直し(拡大)の方向を提示する見込み。まだ“最終決定”ではなく提案・議論段階。参考:厚生労働省
- 併せて、更新制の見直し(更新制の廃止+定期研修を分割受講)といった制度再設計も厚労省案として報じられている。現場の学習・勤務シフトに影響。
これ、現場ではどう響く?
- 3年で受験OKになると、いま3〜4年目の介護職や看護・リハ職が早くケアマネ挑戦の土俵に立てる。事業所としてはケアマネの確保・育成ラインを前倒しでき、配置の穴(産休・退職・病欠など)に対するリスクヘッジがしやすくなる。
いまの受験要件をサクッと再確認(現行)
- 保健・医療・福祉の法定資格に基づく業務or一定の相談援助業務に通算5年以上従事+試験合格→実務研修修了が基本ライン。部会資料の「現状・課題」に明記。厚生労働省
現場の懸念「ケアマネが増えると、介護職が減る?」への対策
- 処遇の“同時底上げ”を見える化
国の人材確保方針では処遇改善・負担軽減・カスハラ対策が柱。
事業所内でケアマネ/介護職の配分と手当設計を可視化して「転出メリット一色」にならない賃金テーブルを作る。
ケアマネは処遇改善加算の対象外なうえに、激務ですからね・・・
「介護職のままでいいや」って人は多いですよね。私も耳にします。 - 若手の早期登用×現場定着の二段ロケット
“5→3年”で若年層の門戸が広がる前提。主任ケアマネのメンター制+段階的ローテで育成、現場側は役割拡張手当・専門加算で魅力を維持。 - 採用を前倒し・内部公募を計画化
127回部会の議題にもある人材確保・職場環境改善の流れに合わせ、欠員前補充+教育期間の確保を“年度運用”に組み込む。 厚生労働省
「試験は難しくなる?いつ受ける?」をデータで整理
公式データ(全国合格率)
- 第27回(2024)合格率:32.1%(受験53,699/合格17,228)=近年で例外的に高い。厚労省の実施状況ページおよび各社まとめ参照。 参考:厚生労働省
- 直近の推移(第23〜27回):17.7% → 23.3% → 19.0% → 21.0% → 32.1%。長期的には15〜25%帯が中心で年変動が大きい。 参考:ウェルミージョブ
制度変更と難易度の関係
- 2018年の要件厳格化期は合格率10.1%まで低下という強い変動が発生(=制度が動く年はブレやすい実例)。 ウェルミージョブ
- 2025/10/27の部会は入口(要件)を“拡大・緩和”方向で議論中(“5→3年”“対象職種拡大”)。施行時期・最終案は未確定。
2027年前後の3シナリオ確率(推計)
過去分布+審議の方向を前提に、全国平均合格率のレンジを置いた“合理的な幅”。(公的な確率公表はないため推計。)
- 回帰(最頻)
合格率20〜25%帯へ回帰。確からしさ:~50%(長期の中心帯に戻る可能性が高い)。 ウェルミージョブ - 初年度やや難化(受験者急増・層の拡散)
15〜20%へ下振れ。確からしさ:~30%(2018年の急落に“制度変動年のブレ”の前例)。 - 高め安定(人材確保色を強める運用)
25〜30%近辺が続く。確からしさ:~20%(2024年並みが続くケース。ただし例外寄り)。
いつ受けるのが得?
- 現行要件で受験可の人:2025〜2026の“二年計画(今年挑戦+翌年で取り切る)”が期待値高め。
2027年は制度変動年の振れが読みにくい。一方、2024年のような“高合格率”の再現は保証されない。 - 要件未達の人:3年案が通れば門戸は広がるが、“受かりやすくなる”とは限らない。過去問×根拠学習で早期に合格点付近へ到達する準備を。

制度変動で合格率に振れ幅ができる可能性もあるから、やっぱり今のうちに受けた方が良さそうですよね。
最新の対策本をチェック!
私も受験には中央法規さんの過去問シリーズを使いました。
分からないところはYOUTUBEや参考書で調べました。
Amazonで10月31日から参考書は発売のようです。
過去問はもう少し先の12月26日予定です。
過去問は対策には必須だと思います。特に問題の言葉の癖を理解していくと、答えに導きやすいってことはやってみて感じました。
リンク
リンク
免責
本記事は厚労省の審議会資料等の公表時点情報に基づく。制度の最終内容・施行時期は今後の法改正・通知で確定。最新は厚労省サイトを確認してください。参考:厚生労働省