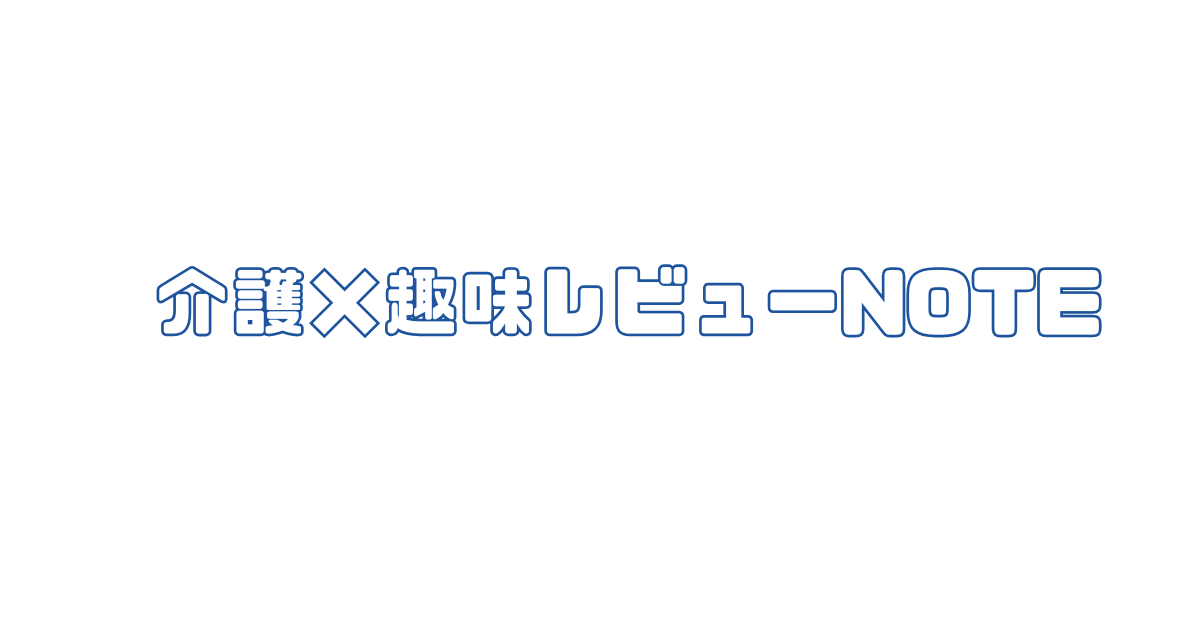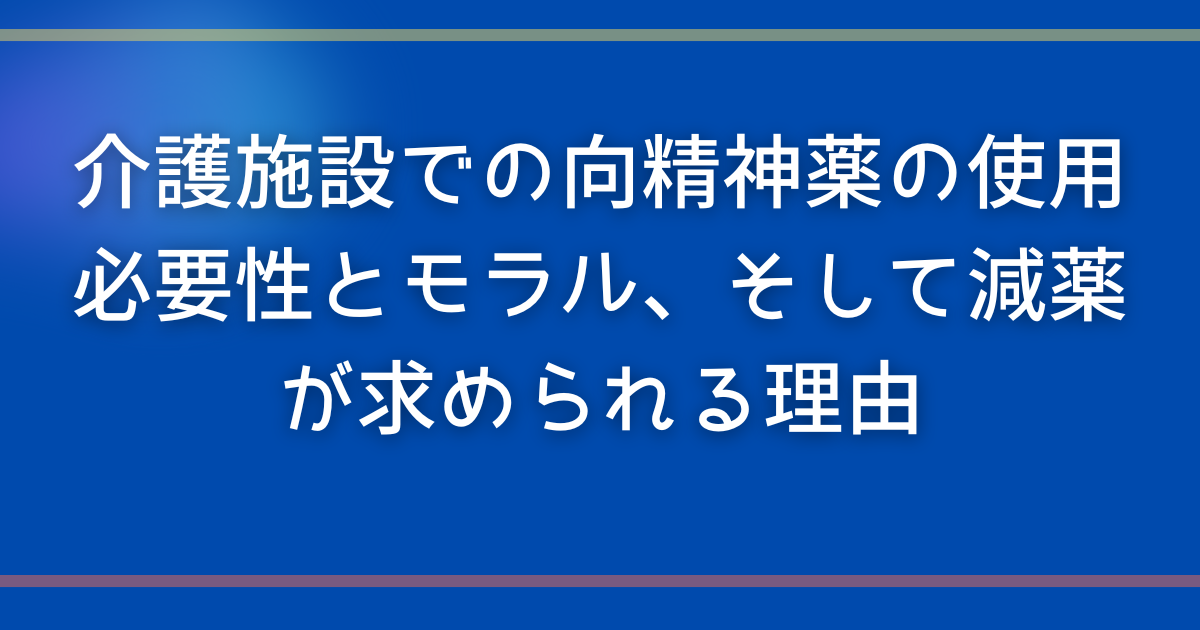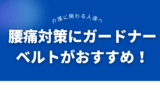はじめに
介護施設では、ときどき「リスパダール(リスペリドン)」や「セロクエル(クエチアピン)」といった薬の名前が聞かれることがあります。これらは一般に「向精神薬」と呼ばれ、認知症のある利用者さんが興奮したり、暴力的な行動をとったり、夜中に徘徊したりして、生活や安全に支障が出る場合に医師の判断で処方されることが多いです。
特に、こうした行動は 認知症の行動・心理症状(BPSD: Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia) と呼ばれ、介護の現場では深刻な悩みの種になっています。スタッフも家族も疲弊し、本人もつらい状態になるため、緊急的に向精神薬が使われることもあります。
一方で、「薬に頼りすぎるのはどうなのか?」「本人の気持ちを無視しているのでは?」というモラル的な問題も指摘され、近年では減薬や非薬物的な対応が強く推奨されています。
皆さんの施設ではどうでしょうか?現実と理想は違うかと思います。
この記事では、介護施設で向精神薬が使われる理由とその課題、そしてなぜ減薬が進められているのかについて、わかりやすく解説していきます。
向精神薬が使われる理由【対応の難しさ】
介護施設で向精神薬が使われる最大の理由は、認知症の方に現れる BPSD(行動・心理症状) への対応です。
BPSDとは、認知症の進行に伴って起きるさまざまな困った行動や心理的な症状のことで、代表的なものには以下があります。
- 暴力・暴言
- 興奮・大声で叫ぶ
- 徘徊して転倒する危険がある
- 幻覚や妄想で不安になり暴れる
- 夜間不眠・昼夜逆転
これらの症状が強く出ると、本人が怪我をしたり、周囲の利用者やスタッフに危険が及んだりするため、どうしても落ち着いてもらう必要があります。
人手不足の現場は特に事故の危険性も出てきますから、薬に頼らざるを得なくなってきます。
ユニットにいる全ての人間が、「その人の対応が上手くできる」ようになれば
あるいは使わなくても大丈夫なのかもしれません。
それができる施設は、どれくらいあるのか・・
きっと皆さんの施設でも「この人はうちの施設だから、薬を使わずにいられる」っていう方いらっしゃると思います。
職員の努力もあり、「本人らしさ」を失わずに生活できている人もいるでしょう。
本来は環境調整や声かけ、見守りといった「非薬物的ケア」が第一選択とされていますが、それでも状況が改善しない場合、医師が向精神薬を処方します。
例えば、リスペリドン(リスパダール)は、興奮や攻撃的な行動を抑える効果があり、少量から始めて短期間使用するケースが多いです。また、クエチアピン(セロクエル)やオランザピン(ジプレキサ)も同じような目的で使われます。
現場のスタッフにとっては「もう手がつけられない」という場面もあり、向精神薬が役立つ場合もあります。医療的にも、本人の苦痛や危険を軽減するために一時的に使うのは合理的な選択といえるでしょう。
実際の現場では、使用することで傾眠が強くなったり、食事が取れなくなるパターンもあります。難しいんです。
ただ、薬を使用しない場合でも認知症の症状で、本人が混乱してる様子が辛そうに私は見えました。
自分を失っていくのが分かってるんじゃないか・・と。
そうした場合、薬の使用もひとつの手段としてはありなのかとも思いました。
モラル的な課題【本人らしさ】【疲弊する現場】
向精神薬は、BPSDの強い方の安全や周囲の平穏を保つために役立つ一方で、モラル的な課題も指摘されています。
一番の問題は、本人の意思や尊厳が軽視されがちになること です。
例えば、介護の現場では「暴れるから」「夜中に歩き回って危ないから」という理由で薬が使われることがありますが、それは本当に本人のためでしょうか?
薬で無理やり行動を抑え込むと、本人の「やりたいこと」や「表現したい気持ち」まで奪ってしまうことがあります。
さらに、過度に薬を使うと、認知症の症状が進んだように見えたり、ぼんやりして転倒しやすくなったりする副作用が起きることもあります。そのため、「施設の管理のための薬」になってしまうリスク があるのです。
施設のスタッフや家族としては、本人の安全と周囲の平穏を守りながら、できるだけ本人らしさを尊重する。そのバランスをどう取るかが大切です。
最近は、「尊厳あるケア(パーソン・センタード・ケア)」という考え方が重視されており、薬に頼らず環境や対応を工夫する方法が推奨されています。本人がなぜその行動をするのか原因を探り、環境や声かけ、活動の工夫で落ち着いてもらう取り組みが増えています。
なぜ減薬が推進されているのか
近年、介護施設では向精神薬の 減薬(げんやく) が強く推進されています。それにはいくつかの理由があります。
まず、向精神薬には 重大な副作用のリスク があるからです。特に高齢者は薬の影響を受けやすく、以下のような問題が報告されています。
- 転倒や骨折のリスクが高まる
- 認知機能が低下し、ぼんやりして生活の質が下がる
- 脳卒中や心臓病のリスクが上がる
- 食欲低下や脱水などで体力が落ちる
こうしたリスクがわかってきたため、国の方針でも「非薬物的ケアを優先する」ことが示され、ガイドラインや研修でも繰り返し強調されています。
厚生労働省の「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」でも、向精神薬に過度に依存せず、介護職員や家族がチームで原因を探り、適切な対応をすることが重要とされています。
海外でも、アメリカやヨーロッパでは「過剰な抗精神病薬使用を減らす」取り組みが先行しており、日本でもそれにならって改善が進められている状況です。
さらに、薬を減らした結果、むしろ表情が生き生きして活動的になるケースも多く報告されており、薬に頼らないケアが本人の尊厳や生活の質につながる という考えが浸透してきました。
参考:
- 厚生労働省「認知症ケアの手引き」
- 日本老年精神医学会「認知症疾患治療ガイドライン」
- NICE(英国国立医療技術評価機構)のガイドライン
まとめ
介護施設で向精神薬が使われるのは、認知症による行動・心理症状(BPSD)が強く、本人や周囲の安全や生活が脅かされるときです。リスパダールなどの薬は、暴力や興奮を抑え、落ち着いて過ごしてもらうために一定の役割があります。
しかし、薬は万能ではなく、副作用のリスクも大きく、本人の尊厳を損ねるおそれもあります。過剰に薬に頼るのではなく、「なぜその行動が起きているのか」を理解し、環境や対応を工夫する「非薬物的ケア」が重要です。
現場や家族としては、医師や看護師と相談しながら、薬の必要性とリスクを理解し、減薬や中止が可能なタイミングを一緒に考えていくことが大切です。
向精神薬は、あくまで「必要最小限」で「短期間」に使うのが基本です。本人らしさを守るために、薬に頼らないケアの工夫を積み重ねていきたいですね。
📚 参考資料
- 厚生労働省「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ninchisho_kaigo.html - NICE (UK) Dementia guidelines
https://www.nice.org.uk/guidance/ng97 - 日本老年精神医学会編『認知症疾患治療ガイドライン(第3版)』医学書院