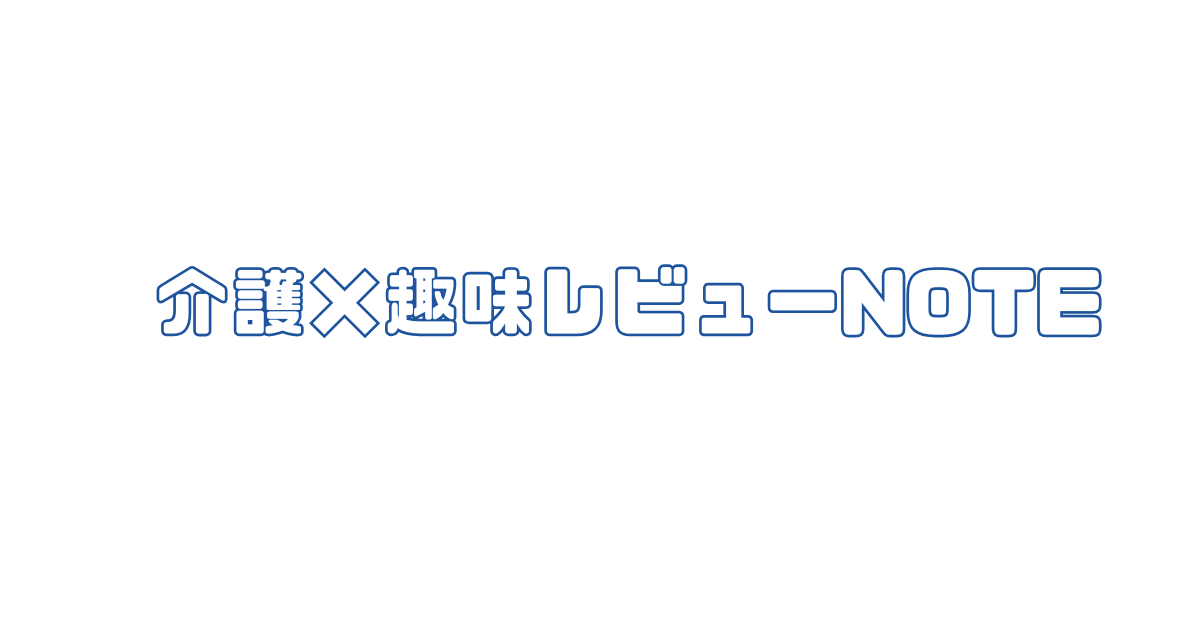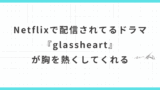看取り介護とは何か?
看取り介護とは、人生の最終段階にある高齢者が、その人らしい最期を迎えられるよう支援する介護のことです。
延命治療ではなく、「穏やかに過ごすこと」「苦痛をできるだけ和らげること」「心の安心感を保つこと」を重視します。
一般的な介護が「生きるための支援」であるのに対し、看取り介護は「命の終わりに寄り添う支援」です。
本人の意思や家族の思いを尊重しながら、残された時間を温かく、静かに支えていくのが特徴です。
このケアは介護職員だけで完結するものではありません。医師、看護師、ケアマネジャー、家族など多職種との連携が不可欠です。
チームで協力し合い、最期までその人らしい尊厳ある時間を守ることが求められます。
言い方は適切ではないかもしれませんが、介護の仕事のやりがいは『看取り』に私はありました。
利用者様との関わり方、施設で過ごした思い出、家族との関わり、
利用者様にとってより良い最期とは?
をチームで話し合いケアを統一していきます。
長い人生の中で、最期に自分達が関わることができるというのは、とてもありがたいことだと思うんですよね。
特に特養などの施設では、一緒にいる時間も長いので思い出がお互いあるでしょう。
最近の利用者様の様子を知っている職員だからこそ、その人らしい看取りを目指したいですよね。
介護の仕事の嫌な面を言えば、
『死に慣れてしまう』ことだと私は思います。
もちろん悲しいです。動揺だって今もします。けど、どこか冷静な自分がいることが、寂しく感じるようになりました。最初の頃は同僚に心配されるくらい泣いてしまいました。
けど、経験を積んできて「こうしなければいけない「家族に伝えなきゃ」など仕事の流れが頭に浮かぶようになってくる。
それがね、少し寂しい。

私だけかな?たくさんの看取りを経験してそう思ったんです
看取り介護の流れと身体的サイン|下顎呼吸やチアノーゼの兆候
看取り介護の現場では、利用者の体と心に起こる変化を敏感に感じ取りながらケアを行います。
死期が近づくと、いくつかの共通した身体的サインが現れます。
代表的なのが「下顎呼吸」と呼ばれる不規則で浅い呼吸です。
これは呼吸中枢の機能が低下して起こるもので、終末期の兆候のひとつです。
また、手足の先が冷たくなり紫色に変化する「チアノーゼ」、
反応の低下、意識レベルの変化も見られます。
介護の仕事を始めた頃、1人夜勤で『もしかしたら危ないかも』という申し送りがあったとき、もう不安で仕方ありませんでした。
呼吸の仕方は人によって違いが多少あります。下顎呼吸の時間が長い人もいれば、短い方もいらっしゃいます。
もう少し大丈夫、と思っていてもすぐに息が止まってしまう方もいました。
逆に、下顎呼吸の時間が長い方もいました。
なのでご家族を呼ぶタイミングが難しい。
こうした変化を察知したとき、介護職は家族への連絡や、医療との連携を迅速に行う必要があります。
家族には「今がどういう状態か」を丁寧に説明し、できるだけ最期の時間を一緒に過ごせるよう配慮します。
| 身体的サイン | 特徴・説明 |
|---|---|
| 下顎呼吸 | 不規則で浅い呼吸。呼吸中枢の機能が低下した状態で、終末期に多く見られる。 |
| チアノーゼ | 血流の低下で手足の先が冷たく紫色に変化する現象。 |
| 反応の低下 | 声掛けや刺激に対する反応が薄くなる。 |
| 意識レベルの変化 | 意識が低下し、呼びかけても反応が鈍くなったり、覚醒しづらくなる状態。 |
家族への声かけと心のケア|現場の実体験から学んだこと
私はこれまでに20人以上の利用者を看取ってきました。その中で強く感じたのは、「心のケア」こそが看取り介護の核心だということです。
利用者さんは、身体の痛みや不安だけでなく、「自分がいなくなること」への恐れや孤独も抱えています。だからこそ、そっと手を握る、名前を呼びかける、静かに寄り添う。
そんな小さな関わりが、どれだけ大きな安心につながるかを身をもって学びました。
また、家族にとっても看取りは大きな試練です。「ちゃんと見送れるだろうか」「これでよかったのか」と迷いや葛藤を抱えている方がほとんど。
私はそんなときこそ、「その人の命を大切に思っていること」が伝わるような言葉をかけるようにしています。
施設での様子を伝えたり、こんな習慣があったんです、とか
今もきっと声が届いてますよ。 とか。
その人らしさを伝えたり、あるいは聞いてあげてください。
難しいですが、利用者様と家族の時間を取ってしまわないように、必要以上の声かけはしないように、私はしています。
特養での看取り介護を通じて得た学びと家族ができること
看取り介護を重ねる中で、私は“命”と“人とのつながり”の大切さを深く実感するようになりました。
ご家族に手紙をいたただいた時にそれを感じます。
職員側は、施設にいる時の利用者様しか知らないけれど、ご家族はそれ以前から過ごして、
色んな思いを抱えているんですよね。
これからも一人ひとりの“その人らしい最期”に関わっていきたいと強く思っています。
看取りの際には、技術的な面で言えば、たいしたことは正直できません。
ご家族で、何か利用者様にしてあげたいという思いがあるなら、顔や口腔内などを専用のウェットティッシュで拭いてあげてください。あとはやはり声をかける。
寄り添うことが大切だと思います。
まとめ|看取り介護で大切にしたいこと
看取り介護とは、命の終わりに寄り添う、とても繊細で深いケアです。延命ではなく、「穏やかに」「その人らしく」旅立てるよう支えることに価値があります。
現場では、下顎呼吸やチアノーゼなど終末期のサインを見極めながら、医療・家族と連携し、限られた時間を丁寧に過ごしていきます。
そして最も大切なのは、利用者や家族の“心”に寄り添うこと。
小さな声かけや手のぬくもりが、大きな安心と癒しをもたらします。
看取り介護は、介護職にとっても多くの学びと気づきを与えてくれる仕事です。命の重み、人生の尊さ、人と人の絆。そうしたものを感じることができます。
あなたが介護の現場でこのブログを読んでいるなら、ぜひ自信を持ってください。
看取り介護は、命のそばで、人の尊厳を守る、かけがえのないケアです。