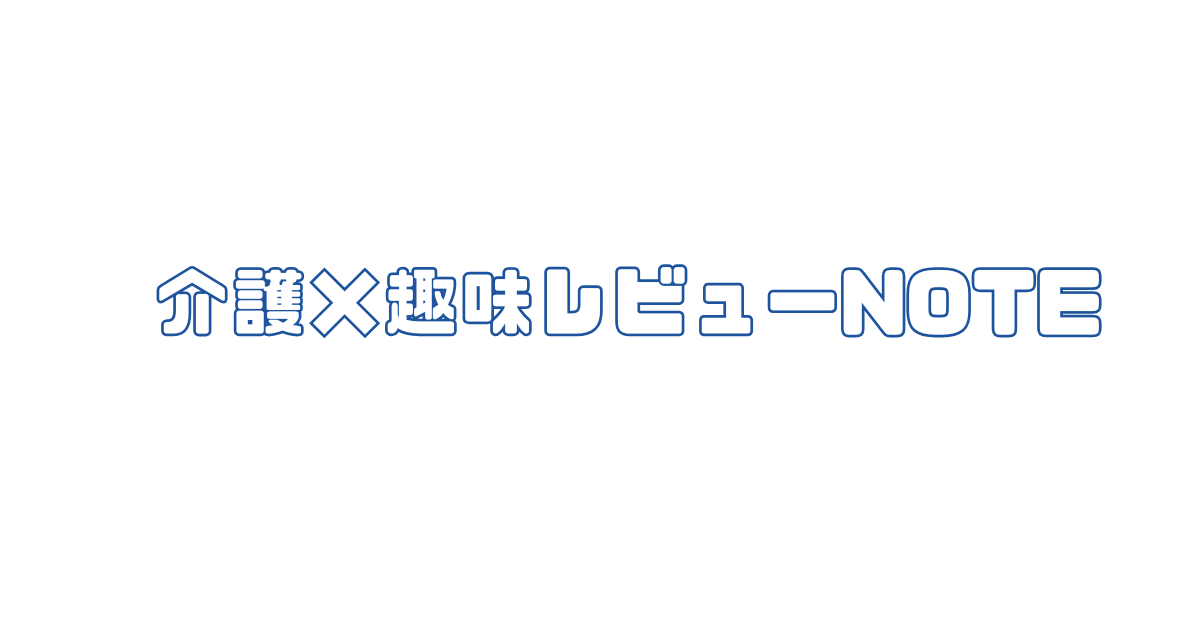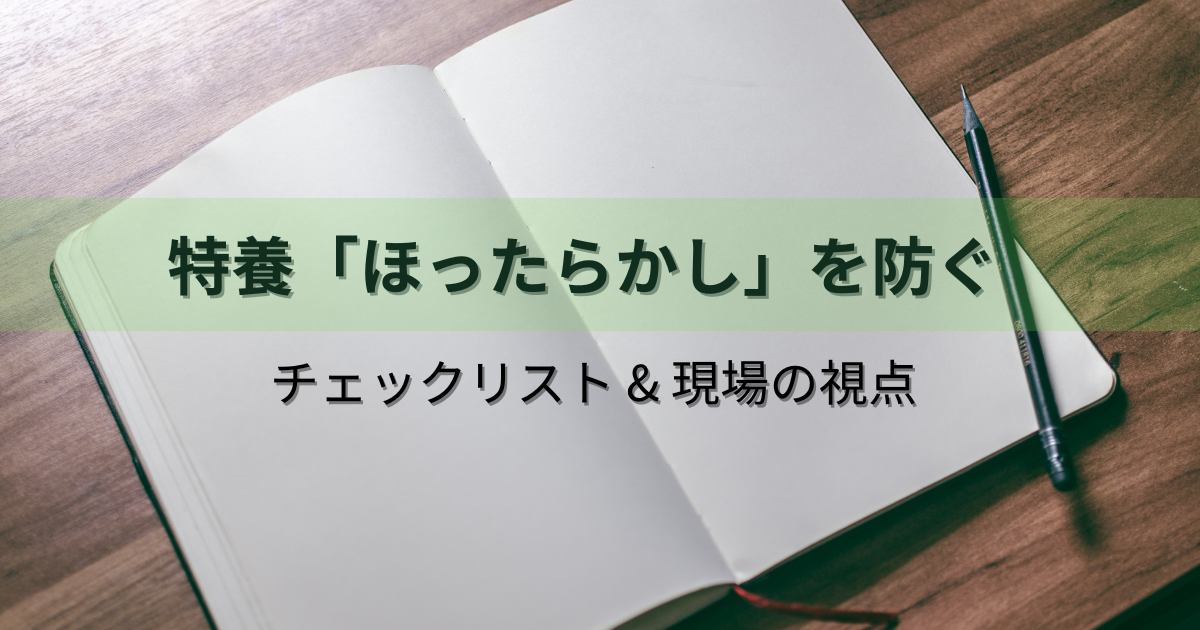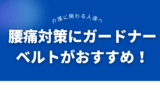介護福祉士として働く私が、家族と現場の両方で使えるチェックリストをまとめてみました。
私の親は大丈夫かな?と疑問に感じたら見てみてください。
このチェックリストのねらいと根拠
“ほったらかし(ネグレクト)”は、声かけの不足みたいなソフト面から、排泄や体位変換、服薬の見守りといったハードなケアまで幅広い。
見た目は小さな“抜け”でも、積み重なるとリスクは一気に跳ね上がります。
このリストは、家族が面会・見学で短時間に確認できるリストと、職員がセルフ点検できるリストに分けて作っています。
基本の声かけ・見守り
——3分以内の反応と“置き去り”を作らない目配り
廊下ですれ違った時に「○○さん、今日は気持ちいい天気ですね」とか、トイレ誘導の前に「そろそろ行きましょうか」と声をかける。これが自然にあるかないかで、入居者さんの表情はまったく違います。
チェックポイント(4つ)
すれ違う職員が入居者へ自然に声かけ(名前+一言でもOK)
呼び鈴・ナースコールに3分以内で反応できる。
ぼーっと一人で長時間放置される人がいない。
職員の視線が届く配置・工夫がある(死角に置き去りがない)
現場のリアル
夕食前後と朝の更衣タイムはバタバタのピークです。ここでどうしても「ちょっと待ってね」が重なると、ナースコールの反応が遅れたり、フロアの端の人に声がかけられない時間ができたりします。
そのすぐ反応できなかった時間の隙間で事故って起きるもの。
制度上、夜勤帯でも「常時配置」が義務化されているので、「人が足りませんでした」は言い訳になりません。だからこそシフト組みとラウンドの工夫が命なんです。
例えば1号室で介助中、9号室でコールが鳴った場合の動きは?この動線をユニットでどう考えてるかで事故が起きるか起きないかに繋がります。
家族が見学で確認するコツ
面会中にナースコールを押してみる。5分以上放置されていたら赤信号。理由説明があっても常態化していれば改善要望を。
フロア全体を見渡して、「呼びかけがなく、黙々と仕事をしているだけの雰囲気」だと要注意。
職員セルフチェックの視点
忙殺時間帯に声かけがゼロになっていないか?
「声かけの質」・・・感情的な声かけが聞こえてくる/無言の時間が多い
「ラウンドチェックリスト」に声かけ項目を入れているか?
清潔・整容
口元に食べかすが乾いたまま、服にシミ、髪が乱れてボサボサ……。これ、本人もつらいし、家族が見たときに「ほったらかされてる?」って直感する瞬間だと思います。
介護福祉士は、清潔ケア=身体を守るケアであると同時に、その人の尊厳を守るケアだと考えています。
チェックポイント(4つ)
口元や衣服に食べこぼしが残っていない
爪・ヒゲ・髪・皮膚の清潔が保たれている
オムツやパッドの交換遅れによる臭いや皮膚の赤みがない
車いすやベッドのシーツが清潔でシワだらけになっていない
これを怠ると…
口の中の残渣(ざんさ:食べかす)→ 誤嚥性肺炎のリスク上昇
交換遅れ→ 皮膚トラブル・褥瘡(じょくそう)の温床
髪や爪の不潔→ 感染症や不快感
清潔・整容の“抜け”は、単なる見た目の問題じゃなく、命に直結するリスク管理の穴なんです。
家族が見学で確認するコツ
面会時に、口元・衣服・爪・髪をさりげなくチェック。
ベッドや車いすのシーツの「シワ・臭い」に注目。
「昨日着替えたばかりのはずなのに?」という違和感があれば、遠慮せず職員に確認してOK。
職員セルフチェックの視点
口腔ケア・整容ケアは時間が守られているか?
清掃・洗濯・交換スケジュールと実際がズレていないか?
忙しい日でも最低限の清潔ケアを優先できているか?
褥瘡=必ずしも“放置”とは限らない
「褥瘡(じょくそう)がある=ほったらかし」と思われがちですが、実際には状況によってはすぐに体位交換できないケースもあります。
たとえば…
看取り期では、体位交換をすることで呼吸が乱れることがあります。
この場合は「ナースが来るまで」「大事な家族を待っている間」などは、体を動かさず、エアマットやジェルマットなどで圧を逃がす対応を取ることがあります。
マットレスの質によっては褥瘡のリスクが大きく変わります。固いものを使っていると短時間でも皮膚トラブルになりやすいため、体交の頻度だけでなく用具選びも重要です。
つまり褥瘡ひとつ取っても、「怠けている」ではなく、きちんとした理由と判断があるケースがあるということ。
だから家族は「なぜこうなっているのか」を冷静に質問し、職員側は「今の判断理由」をしっかり説明する。このキャッチボールが大事です。
食事・水分・服薬
食事・水分・服薬は、誤嚥(ごえん)・脱水・誤薬という三大リスクと直結。ここは“ほったらかし”を一発で見抜ける領域でもあります。
現場のコツは「姿勢づくり → 一口量 → 目線と声かけ → 確認」のループ。スピードより待つ力が大切です。
家族向けチェック(4つ)
食事形態(刻み・ミキサー・とろみ等)が本人の嚥下レベルに合っている
座位姿勢がとれている
水分オファーがこまめ(お茶・水が手元にあり、促しがある)
服薬の見守り(飲み込み確認・声かけ)がある/飲み残しの管理がある
職員セルフチェック
口中残渣の確認→次のひと口。
声かけ:急かさない。「ゆっくりどうぞ」「飲み込んでから次へ」。
5つのR(服薬):Right person / drug / dose / time / route(本人・薬剤・量・時間・経路)。
配薬は一人分ずつ完結。
記録:食事量(主食・副食・水分)とむせ・咳・残し・拒否をセットで記載。
“赤信号”になるサイン
食事中にむせ・咳が繰り返し/声が濡れた感じに変化
水分摂取が極端に少ない(夕方の尿が濃い・口唇乾燥)
食前・食後の姿勢調整や口腔ケアが無い(口の中に残って終わり)
看取り期との境目の配慮
看取り期は無理に食べさせない判断もふくまれます。
水分や口腔ケア中心にシフトし、本人の楽さを最優先。
ここでも難しいのが、水分や点滴。
「水分を入れれば良い」と思われがちですが、体が吸収・排出できない状態になると、痰(たん)が増えて絡む → 呼吸が苦しいという事態につながります。
吸引をすればいいというわけでもなく、その時の利用者さんの表情を想像してみてください。
苦しそうな様子なんです。もちろん痰が取れて楽になりますが、
またしばらくして、痰が絡んでしまうこともあります。
なので、「どこまで水分を入れるか」「点滴をするかどうか」は医師・看護師と家族で一緒に判断するしたほうがいいです。
介護の立場で大事なのは、
- 今の状態で水分摂取が苦痛になっていないか観察する。
- 呼吸音や痰の絡みの変化をナースに報告する。
- 家族に「なぜ今は水分を控えているか」を説明できるようにする。
- 家族には「なぜ今は減らしているか」「むせのリスクと苦痛」を丁寧に説明。
信頼関係に繋がるのでどういったリスクがあるか?も話したほうがいいと思います。
「点滴をしない理由については、こちらのクリニックさんの説明がわかりやすいです — たんぽぽクリニック 」
家族が面会でできる“ひと押し”
「今日は水分どれくらい飲めました?」と数字で尋ねる(例:600ml)。
「むせが増えた日はありましたか?」と変化を聞く。
食後に口の中をそっと確認(義歯の装着、残渣の有無)。
服薬は飲み切ったかを一緒に見届ける(職員に声をかけてOK)。
排泄・体位変換・痛み
排泄や体位変換は、入居者さんの生活の質(QOL)に直結するケアです。
でも現場が忙しいと「ちょっと待っててね」になりがち。これがほったらかし感を強くさせてしまいます。
「排泄は我慢するもの」「痛みは仕方ない」——そんな空気を放置すると、身体だけでなく心の萎縮にもつながります。
家族向けチェック(4つ)
- トイレ誘導の声かけが定期的にある(我慢前提になっていない)
- ベッド上での体位変換が2〜3時間おきに行われている(目安)
- 褥瘡予防の工夫(クッション・マットレス)が見られる
- 痛みや不快のサインに反応して職員が対応している
重要なのは仕組みづくり。
トイレ誘導は「2時間ごと」などアラートやルーチンで回す
体位変換は「他の職員任せ」ではなくリスト化と引き継ぎで抜けを防ぐ
痛みや不快の訴えはバイタルや記録に残すことで“我慢させっぱなし”をなくす
家族が見学で確認するコツ
オムツ交換やトイレ誘導の声かけがあるかを耳でチェック
褥瘡の有無を質問したら、職員が「場所・状態・対策」を即答できるか
ベッド周りに体位変換クッションやマットが備えられているか
ご本人が「痛い」と言ったとき、職員が立ち止まって対応しているか
職員セルフチェックの視点
「尿意・便意サイン」を見逃していないか?(手をもじもじ、落ち着きない行動、表情)
「体交リスト」と「実際の巡視」が一致しているか?
痛みの評価(0〜10スケール)を看護と共有できているか?
生活・交流・尊厳
特養のケアは「生きるために必要なこと」だけじゃなく、“その人らしさ”を支えることが本質です。
食事や排泄といった基本ケアが整っていても、交流がなく孤独な状態が続けば「ほったらかし」と感じられてしまいます。介護福祉士が大切にしているのは、“生活の彩り”を意識的につくることです。
利用者さんの良き理解者であること、を私は意識しています。
家族向けチェック(4つ)
- 好きな音楽・趣味・会話など、個別の関わりがある
- レクリエーションが苦手な人に代替の過ごし方が用意されている
- 眼鏡・補聴器・義歯などの私物がきちんと管理されている
- プライバシー配慮(カーテン・声の音量)が守られている
正直いうと、日々の業務に追われていると「趣味や交流」は後回しになりがちです。
でも、声かけや一緒に写真を見て思い出話をするなどたった数分の関わりで、その人の表情が変わります。「ほったらかし」を防ぐのは、小さなコミュニケーションの積み重ね。
“流れ作業”にならずに向き合えているか。
何を言ったら笑ってくれるか?
今日はどんな気分なのか?
そしてその人をちゃんと見ているか?
日々のコミュニケーションの中でそんなことを思いながら、私は利用者さんと接していますが、絶対に上手く出来てるというわけでもありません。
やはり人手不足だったり、拒否があったり、うまく回らなかったりで、寄り添った会話ができないこともあります。
それでも声を荒げることはありません。そこは自信を持って言えます。
家族が見学で確認するコツ
面会中、職員が利用者さんの名前で呼んでいるかを観察
補聴器や義歯が放置されていないかをチェック(なくす=生活の質低下)
レクリエーションやイベントで「参加が難しい人」に別の配慮があるか聞いてみる
職員セルフチェックの視点
ケア記録に「趣味・好きな話題」が記載され、実際に活用されているか
レク参加の有無にかかわらず孤立している人に短時間でも声かけがあるか
プライバシーに配慮できているか(排泄・入浴・処置時のカーテンや声の大きさ)
利用者さんの今日の心の鍵を見つける
ある入居者さんは、口数が少なくほぼ無表情。散歩にもなかな行ってくれない。
けれど、ある日ふと昔の演歌を流したら、口ずさむように声を出されたんです。
その瞬間、「あ、この人のキーワードはこれだ」と感じました。
歌いながらだったら、散歩に気持ちよく行ってくれる。
施設で働く職員ならあるあるかもしれませんね。
生活の中でその人のアイデンティティをどう引き出せるか・・・これが“ほったらかし”を防ぐコツだと思っています。
今日の心の鍵、というのは次の日には変わっているかもしれないからです。
今日は「外を散歩してみたい」「今日は静かに新聞を読んでいたい」など。
好きな歌の場合は、変わらないと思いますが😆
まとめ:ほったらかしを防ぐのは“気づき”と“仕組み”
「ほったらかし」は小さな“抜け”“我慢”が積み重なって、入居者・利用者の命と尊厳を揺るがす状態になる。その防止の鍵は、現場の気づきと仕組みの整備にあります。
キーファクター:気づき
家族や職員が「何か違う」と思ったら、その直感を信じて動くこと。
呼び鈴の無応答、表情の変化、むせの増加、排泄の遅れ、不潔感など、小さなサインを見落とさない。
看取り期・嚥下機能低下期では、以前良かったことが急に悪くなることがあるので、「変化」がいちばんのアラーム。
「なぜこうしているのか」の理由を施設側が説明できるかどうか。説明が曖昧なら要注意。
キーファクター:仕組み
記録と引き継ぎの強化:見守り・排泄・体交・服薬・食事・水分などの記録を丁寧にし、交替時・夜勤明けに引き継ぎできるようにする。
研修・教育:ネグレクト・尊厳・高齢者虐待防止法・終末期でのケア判断などを職員に繰り返し学ばせる。
モラル・専門知識両方。 医療・看護連携:医師・看護師との情報共有体制。特に点滴・水分補給・看取り期の判断はケアのみの職員には難しいので、ナースや栄養士などチームで相談できる環境をつくる。
適切な器具・環境整備:ジェルマットや軟らかいマットレス、圧を逃がすクッションなど。環境が悪いと体位変換だけでは対処できない。
家族とのコミュニケーション:家族をケアのパートナーとして尊重し、ケアの内容・状態・選択肢を共有できること。「なぜこのタイミングで体交しないのか」「なぜ水分を控えているのか」等の説明責任を果たす。
ほったらかしを防ぐのは、“小さな異変を見落とさないこと”と“判断できる体制を整えること”です。ケアには「人の温かみ」が不可欠ですが、それだけでは不十分で、制度・人員・環境・教育が噛み合って初めて“安心できる特養”になる。
人手不足がこの噛み合わせをずらしてしまうんですけどね…
それでも頑張ってる介護職員が多いんです。給料もいいわけではないけれど、一生懸命やってる人が大半です。
一生懸命やっていても、事故は起きてしまうし、どうしてもすぐに行けない瞬間もあります。どっちも手が離せない状況になることだってあります。
もちろん「ほったらかし」は良くない。
でも、現場の厳しさや職員の努力も、一緒に理解していただけたら嬉しいです。
参考:高齢者虐待防止の基本(定義・ネグレクトの位置づけ)→ 家族も施設も“疑い段階”から対応してよい根拠に。厚生労働省より